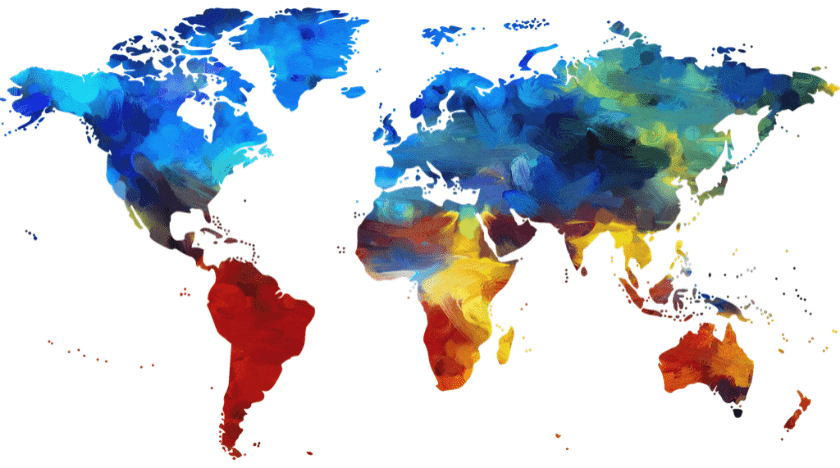
国際離婚の国籍と姓
グローバリゼーションが進展する中で、日本人が外国人と結婚するケースが増えています。また、国際結婚の増加に比例するかのように離婚する国際カップルも少なくありません。
国を超えた結婚・離婚ならではの問題点も存在しています。ここでは外国人との離婚にまつわる様々な問題を整理していきます。
夫婦の国籍は変わらないが、子供は国ごとで異なる
国籍が異なる者同士の結婚を渉外婚といいます。 現在、国際化を背景に渉外婚が増えており、それに伴って渉外離婚も増加しています。
それぞれの国の事情が異なることから様々な問題点が生じています。
例えば、外国人と結婚して子供が生まれた時、相手が自分と子供を置いて帰国してしまったがどうしたらいいでしょうか?離婚したいけれど、相手の国では離婚を犯罪とされ、認められないがどうしたらいいでしょうか?など、結婚した時には想像もできなかった問題が、離婚を契機に色々と起こってくるものなのです。
ちなみに、結婚と国籍のことを混同してしまう人がいますが、結婚と国籍は別の問題です。外国人と結婚したからといって外国籍になるわけではなく一緒に暮らすためには、配偶者ビザを取得することでその国に居住する許可を得ることになります。
離婚した場合も同様で、離婚したからといってすぐに帰国する必要はありません。生活の拠点が日本にあれば、定住者としての在留許可を得れば、日本に定住することは可能ですし、その期間が長い場合は帰化すことで日本国籍を取得することもできます。
子どもの国籍は国によって取り扱いが異なりますが、日本の場合は父または母が日本人であれば、どこで生まれても日本国籍を取得できます。
どこの国の法律に従うか
渉外離婚の難しさは、 どこの国の法律に従うべきなのかから考えなければならない点です。
日本においては、2007年1月から施行された法の適用に関する通則法27条(離婚)25条(婚姻の効力)によって、
- 離婚の時の夫婦の本国が同じ場合
- 夫婦の本国は異なるが、常時居住している地の法律(常居所地法)が同一の場合
- 夫婦の本国が異なり、夫婦で常時居住している地もない場合
※ここでの、常居所とは、人が相当長期間にわたって居住する場所のことで、単なる居所とは異なります。常居所は、居住の年数、目的、状況等を個別具体的事情をもとに、総合的に判断して認定されます。
のそれぞれについて、どこの法律に従うべきかを定めています。居住地が日本である場合は、基本的に日本の法律に従うことが原則だと考えれば良いでしょう。
日本では離婚はプライベートな問題で、基本的には夫婦の話し合いで決めるべきだとの考え方をとっています。しかし、国によっては離婚そのものを認めていない国もあります。
また、一般的に何らかの形で裁判所が関与する国が多く、当事者間だけで離婚の声をしたのでは離婚の成立が認められないケースも考えられます。
したがって、渉外離婚の際には個々の国の違いを念頭に、調停や訴訟などあらかじめ裁判所が関与する形態をとっておくとよいでしょう。
慰謝料や財産分与が発生した場所に裁判権がある
渉外離婚の場合、結婚生活を送っていた場所の裁判所に裁判権があるとされています。ただし、離婚に伴って慰謝料や財産分与の問題が発生した時に、夫婦の様々な問題も抜きには考えられません。そこで、日本ではこれらの問題を解決するにあたり、法の適用に関する通則法27条、25条が適用されるべきとの考え方が支配的になり、現在に至っています。
ちなみに、相手の住所が日本にない場合でも、相手が配偶者を遺棄したり、行方が分からなくなっているようなケースでは、日本の裁判所での 裁判が認められると解釈されます。
子供の問題を含め専門家のアドバイスを
子供がいる場合、親権や身上監護権 をめぐる解釈が国によって異なるので、単なる法理論で決することができない問題が発生します。そのため夫婦には、互いに子どもの福祉の観点に立った合意形成が求められるわけですが、どうしても夫婦間では解決できない問題も存在します。
その場合、最終的には裁判所を介して判断することになるわけですが、どこの国の法律に従うかにはいくつかの条件があります。
親子間の法律関係を定める法の適用に関する通則法32条には次の条項があります。
- 子の本国法が父母の一方の本国法と同一の場合には子の本国法
- その他の場合には子の常居所地法
また、どこの国の裁判所で行うかは、夫婦の離婚の問題を扱う裁判所で行うとの考え方が一般的です。これはある意味で、子の本国法、または子の常居所地法という趣旨には沿いませんが、実際には、夫婦と子どもは同じ場所に居住していることが多く、夫婦が裁判を行う場所=子どもの常居所地となるほうが多いです。
通則法32条の規定は、親権者指定・監護者指定のほか、面会交流・子の引渡し等にも適用されます。
2014年4月よりハーグ条約が発効されましたが、渉外離婚には法律の適用レベルかは複雑な要素が絡み合っています。実際に離婚する場合は弁護士や児童福祉などの専門家のアドバイスを求めることが無難です。
ハーグ条約の概要
増加する国際結婚・離婚と「子の連れ去り」
1970年には年間5,000件程度だった日本人と外国人の国際結婚は,1980年代の後半から急増し,2005年には年間4万件を超えました。これに伴い国際離婚も増加し,結婚生活が破綻した際,一方の親がもう一方の親の同意を得ることなく,子を自分の母国へ連れ出し,もう一方の親に面会させないといった「子の連れ去り」が問題視されるようになったほか,外国で生活している日本人が,日本がハーグ条約を未締結であることを理由に子と共に日本へ一時帰国することができないような問題も生じていました。
子の利益を守る「ハーグ条約」とは?
世界的に人の移動や国際結婚が増加したことで,1970年代頃から,一方の親による子の連れ去りや監護権をめぐる国際裁判管轄の問題を解決する必要性があるとの認識が指摘されるようになりました。そこで,1976年,国際私法の統一を目的とする「ハーグ国際私法会議(HCCH)
」(オランダ/1893年設立)は,この問題について検討することを決定し,1980年10月25日に「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約(ハーグ条約)」を作成しました。2018年12月現在,世界99か国がこのハーグ条約を締結しています。(締約国一覧(PDF)
)
なお,ハーグ条約とは,HCCHで作成された30以上の国際私法条約の総称を指すこともありますが,ここでは「国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」のことを「ハーグ条約」と表記することにします。ハーグ条約の仕組み
国境を越えた子の連れ去りは,子にとって,それまでの生活基盤が突然急変するほか,一方の親や親族・友人との交流が断絶され,また,異なる言語文化環境へも適応しなくてはならなくなる等,有害な影響を与える可能性があります。ハーグ条約は,そのような悪影響から子を守るために,原則として元の居住国に子を迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定めています。
(1)子を元の居住国へ返還することが原則
ハーグ条約は,監護権の侵害を伴う国境を越えた子の連れ去り等は子の利益に反すること,どちらの親が子の監護をすべきかの判断は子の元の居住国で行われるべきであること等の考慮から,まずは原則として子を元の居住国へ返還することを義務付けています。これは一旦生じた不法な状態(監護権の侵害)を原状回復させた上で,子がそれまで生活を送っていた国の司法の場で,子の生活環境の関連情報や両親双方の主張を十分に考慮した上で,子の監護についての判断を行うのが望ましいと考えられているからです。
(2)親子の面会交流の機会を確保
国境を越えて所在する親と子が面会できない状況を改善し,親子の面会交流の機会を確保することは,不法な連れ去りや留置の防止や子の利益につながると考えられることから,ハーグ条約は,親子が面会交流できる機会を得られるよう締約国が支援をすることを定めています。










